SEO・WEB用語
SXO
SEO・WEB用語
SXO

【目次】

WEBマーケティングの手法には、リスティング広告、SNS(Youtubeやtwitterなどの活用)、MEOなどさまざまな方法がありますが、ウェブサイトへのお客様訪問を増やす対策の中心は、やはりSEOでしょう。
ただし、検索順位を上げることにとらわれすぎると、かえって順位が上がらない、ということがよくあります。
検索エンジンのアルゴリズムの変化・進化の中で、以前のように小手先の対策方法では効果が上がらなくっているからです。
そこで注目されているのが「SXO」という考え方です。
この記事では、SXOとは何か?についてご紹介し、
「SEOとSXOの違い」「SXOの具体的な方法」について分かりやすく解説して行きます。
SXOの説明に入る前に、SEOについて確認しておきましょう。
SEO (search engine optimization) は、
「検索エンジン最適化」と訳されています。
会社でホームページを運営している場合、その商品やサービス・エリアなどに関連するキーワードで検索したときに、上位に表示されていれば、多くの人に見てもらうことが可能になります。
この際に、検索結果を決めるシステムが検索エンジンです。
検索エンジンは、順位決めのための様々な指標+独自の計算式で決定するのですが、これを「アルゴリズム」といいます。
つまり、SEOとは、「検索順位を上げることを目的」に、タグやコンテンツを最適なものにする対策と言えます。
検索エンジンというロボットに最適化することで
検索順位を上げることを目指す、ということにあります。
次に、SXOについてご紹介します。
SXOは、seach experience optimization の略で、
日本語では「検索体験の最適化」と訳されています。
では「検索体験の最適化」とはどういうことでしょうか?
Googleなどで検索する人は、「調べたい」「見たい」などの意図をもって検索結果からwebサイトを探します。
検索を通じてホームページに訪れてくれた人に
「最高の満足」を提供すること=「検索体験の最適化」ということです。
SEOとSXOについて簡単に見てきましたが、
SEOが、検索エンジンという「ロボット」を対象にしているの対し、
SXOは、「人」の満足にフォーカスしていることがわかります。
では、なぜSXOという概念が注目されているのでしょうか?
それは、検索エンジンの進化と関係していて、
近年、SEOそのものの転換と実施すべき対策の変化が基礎にあります。
SXOとSEOは違うものとして評価されることが多いですが、
実は、SXOこそ、新時代のSEOの中心的な考え方だと言えるのです。
では、検索エンジンの変化とSXOが注目されている理由をご案内します。
ロボット型の検索システムが始まったのは1996年以降ですが、
その当時はまだ検索エンジンも今ほど高度ではなかったですので
質の悪いウェブページが上位表示されうることが常態化していました。
例えば、以下のような手法が横行していたのです。
などなど、単純な「ロボット対策」で効果が上がっていました。
ですが、この状態ですと、人々は検索システムを使わなくなります。
検索しても、いいコンテンツに巡り会えないからです。
そこで、Googleは検索エンジンのアップデート(アルゴリズム変更)を始めます。
| 2011年 | パンダアップデート コンテンツの質が低いページの順位を下げる |
|---|---|
| 2012年 | ペンギンアップデート 順位を上げるためだけの悪質リンクにペナルティーを課す |
| 2015年 | ランクブレイン AI導入で、検索意図により近い検索結果を表示する |
「パンダ」「ペンギン」の2つのアップデート導入は検索順位に革命的な変化を起こし、幅を利かせていた小手先の手法は通用しなくなり、順位低下するだけでなく、大量リンク・ワードの大量埋め込みなどは、「スパム」としてペナルティーを受けるようになったのです。
これらのアップデートによって「コンテンツの質」が強く意識されるようになり、
2016年くらいから、SXO(検索ユーザーの満足度)という考え方が広まっていったのです。
さらに、2024年3月に
「ヘルプフルコンテンツシステム」が検索エンジンコアアルゴリズムとして導入されました。
これは、AIによって「ユーザーのために作成した独自性のある有用なコンテンツ」と判定されたウェブページの検索順位が上がりやすくなるという仕組み。
(「人にとって役立つコンテンツ」を上位表示させるアルゴリズム)
ですので、今後は、SXOの考え方で作成されたコンテンツがさらに上位化しやすくなり、SEO対策自体も、ブラッシュアップが必要になって行きます。

例えば、検索エンジンは今、
などをモニターし、各ワードの検索順位を決めるようになっています。
閲覧時間が長いということは、
書かれている内容が、「ユーザーのニーズと一致している」ことを示していますし、
何度も見に来る率(リピート率)が高いということは、
「ユーザーの評価が高い」「有益なページ」と判断されるわけです。
このように現在では、様々な指標と評価基準によって「閲覧者満足度」から検索結果を決めるようになっているのです。
一般的には、
SEO = 検索エンジンというロボットへの対策
SXO = 検索を利用した閲覧者(ユーザー)のための対策
という感じで、対立的なものとして認識することも多いですが、
検索エンジンは今、ユーザーファーストのWEBページ・コンテンツを求めていますので、現実は、SXOを意識したWEBページ改善がSEO対策であり、検索順位を向上させるポイントなのです。
SEOは、SXOを中心に考え、組み立てて行くことが必要な時代になっているのです。
…など、SEOは、上記のようなSXOに基づいた施策が必要になります。
では、実際にどのような施策がSEO効果を高めるのか、具体的に見て行きましょう。
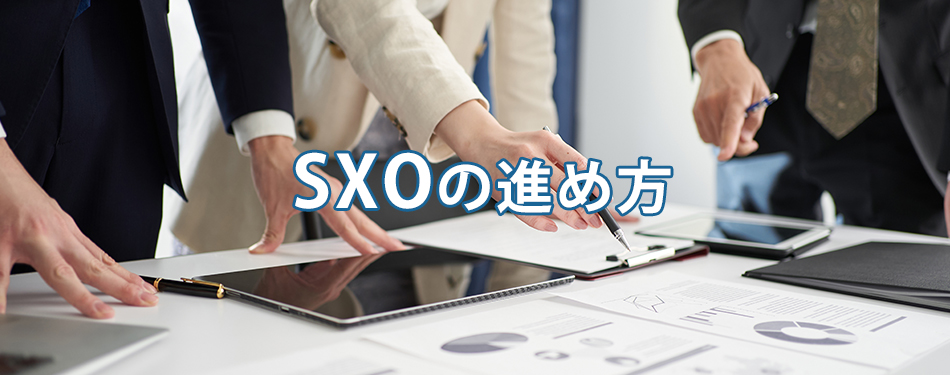
ここまでSXOの意味やSEOとの関係などについて説明してまいりました。
では、どのようにSXOを進めて行けばいいのか、SEO改善ポイントとともに見て行きましょう。
SXOとは「検索ユーザーの検索意図に応えるコンテンツを提供して、満足度を最大にすること」にあります。
ある検索キーワードに対して、コンテンツはどのような情報が必要でしょう?
読み手(閲覧者)は何が知りたいのでしょうか?
どのような言葉、書き方、伝え方がいいでしょう?
こうしたことを徹底的に考えて、文章を執筆して行きましょう。

また、たとえばGoogle検索で
「マラソンシューズとは」
「マラソンシューズ 必要?」
「マラソンシューズの値段」
「マラソンシューズ 通販」
など
検索者が入力したワード(検索クエリ)によって、
検索者が検索した目的⇒書くべき内容(閲覧者が読みたい内容)は違ってきます。
企業のホームページではどうしても
「自分たちが伝えたいことを書く」ことが中心になりがちですが、
それと同時に「閲覧者どんな情報を得たいのか?」を把握し、
「どのように伝えれえばわかりやすいか」を考え、
ユーザーに最高のコンテンツを提供しようとする姿勢が大切となります。
ユーザーファーストのコンテンツ作り=SXOコンテンツ対策であり、
これが「コンテンツSEO」の主要な考え方ととなります。
コンテンツ作成する前に、
「誰に向けて」「どのような内容を」を伝えるのか?をしっかり考え、
そのページの「大見出し」「小見出し」を整理して、流れを考え、
閲覧者が「わかりやすい」「なるほど!と感じる」コンテンツに仕上げるようにしましょう。
またタイトルタグ、ディスクリプションタグのキーワードが、閲覧者の意図や、ページ中の文章と一致しているか、再確認をおすすめします。
【まとめ】
SXOは「閲覧者の最高体験」のことであり、
それはモバイルから検索し、サイトにアクセスした人にも「最高の体験」を提供しなければなりません。
これを「モバイルフレンドリー」といいます。
スマートフォンなどのモバイル端末で「見やすい」「読みやすい」こと。(デザイン、文字サイズ)
「さくさくページが表示され」「動きが軽い」などモバイルでの操作性=ユーザビリティーも非常に重要視されます。(表示速度、安定性)

検索エンジンが「モバイルファーストインデックス」を導入し、
検索順位は「モバイル情報」を基に決定されるように移行しています。
ですので、スマホSXOとも呼ばれる「モバイルフレンドリー」は
徹底的な対策が必要です。
モバイル対応デザインとしては
「レスポンシブデザイン」を採用することをすすめします。
そして、運営するサイトがモバイルフレンドリー状態になっているかどうかをチェックするには、Googleが提供する「PageSpeed Insights」などを使ってチェックし、もし問題が見つかったら修正して行きましょう。
【まとめ】
モバイルフレンドリーであることを以下の方法で確認しましょう
SXO「検索ユーザーの最高体験」での重要な要素に、「表示スピード」があります。
表示速度が遅いと、閲覧者はストレスを感じ離脱します。
特にスマホ表示では、負荷のかかるデザインシステムや不必要に大きな画像を表示していることなどが原因で、表示速度が落ち、ユーザーが快適に閲覧できないものになりやすいので注意が必要です。
また、「閲覧者の意図とは別に、勝手に自動で動くデザインシステム」は
閲覧者の目に負荷を与えたり、不快感を持たれる場合がありますし、
「見やすいリンクがない」と、
関連ページを探そうと思っても見つからず、
ユーザーの利便性を損ないます。
閲覧者にストレスを与えない・快適に読んでいただき、調べていただける
シンプルで美しいデザインで見やすい
…そんなホームページになっているか見直ししてみましょう。
SXOに取り組むメリットは、閲覧者により良い体験体験を提供して、自社のイメージアップにつながり、集客力アップの可能性も引き上げてくれます。
【まとめ】
快適な表示速度と閲覧環境を実現しましょう
SXO(検索ユーザーの最高体験)を考えるとき、閲覧者の個人情報などを守るセキュリティーの強化は不可欠です。
ホームページ閲覧者が、ホームページ上で入力した個人情報(氏名・メールアドレス・電話番号・クレジットカード情報など)が、悪意のある第三者に盗まれないようにするためのセキュリティーは必ず行いましょう。
そのための施策として「通信の暗号化」があります。

ホームページサーバーと閲覧者の間の通信に侵入して、
何者かが「情報を盗む」「データを改ざんする」などを防ぐためには
「SSL対応」(HTTPS化)を行うことは基本中の基本です。
今後は、SSL対応していないビジネスホームページは、
検索で上位表示できず、「誰も見に来ない」状態になって行きますので、
SSL対応をしっかりと行い、
ホームページ閲覧者・ユーザーを守り、ホームページを守りましょう。
SSL対応(HTTPS)で「ユーザーの個人情報を守る」ことは必須です。
自社でサーバーを管理・運用している場合は、サーバー内の機能で簡単に「SSL対応」設定することができますので、ぜひ確認し実施してください。
SXOの考え方を理解し、SEO対策にとりれて対策することの意味を
ご紹介してまいりましたが、参考になりましたでしょうか。
「SEOホームページ」では、
SXOの考え方を基にしたSEOに強いホームページを制作しておりますので、
どんなことでも気軽にご相談ください。
著者:SEOコンサルタント・SEOホームページ代表 占部圭吾

【関連ページ】